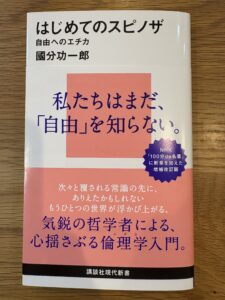新書は面白い12.
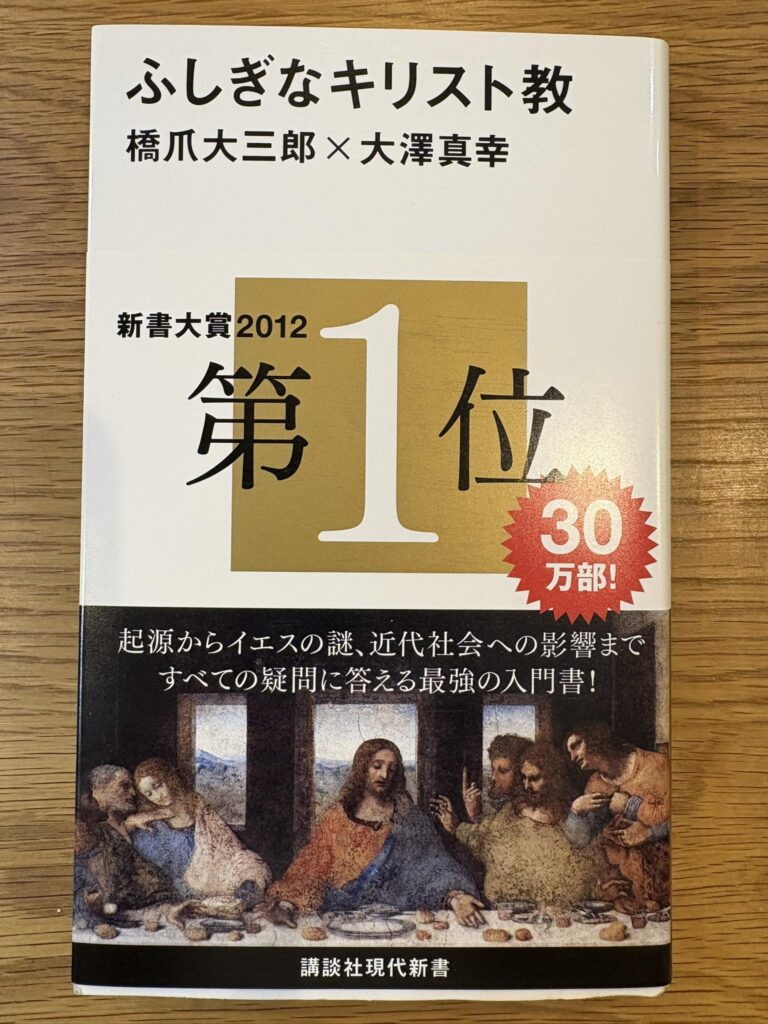
『ふしぎなキリスト教』橋爪大三郎・大澤真幸 講談社現代新書
映画「教皇選挙」がすごく面白かった。どの上映回も満席。まさに現在(2025年5月)、実際にバチカンのシスティナ礼拝堂でコンクラーベの投票が始まっているところ。キリスト教への関心が高まっているタイミング。
自分はカトリックの幼児洗練を受けていて、子供の頃は日曜日は教会に通っていた。成人してからは回数はめっきり減ったが、たまーに思い出したように教会のミサに参加することがある。妻には、エセクリスチャンとからかわれてる。
ミサの中で語られる聖書に出てくるお話。本当のこと言うといまいち意味がよく分からないことが多くて。
ぼーっとミサに出てるのではなく、いつかはキリスト教のこときちんと学んでおきたいな、とミサに参加するたびに感じていた。
大学では社会学を専攻。社会学では必須だったマックスウェーバー『プロテタンティズムの倫理と資本主義の精神』、通称「プロリン」と呼んでた、を学ぶ。
キリスト教の精神が近代資本主義の発展の土台になったと論じた古典的名著として超有名。
大学では、とても重要な著作として、教授もゼミの先輩方も語ってたけど、自分は情けないことに、いまいちそのスゴさをよく分からなからないまま卒業。
共著者ふたりの対話によるこの新書を読んだことで、だいぶ頭の中の霧が晴れました。
そして、西欧を知るためにはキリスト教を理解していることが大前提だということもよーくわかった。プロリンの理屈もね。
本書は、まずはキリスト教の土台となっているユダヤ教の特長について語ります。その後イエス・キリストについて。ユダヤ教との類似点、相違点をわかりやすく説明。最後はそのキリスト教がいかに西欧を作り出したのかについて。
対話形式なので、それぞれの説明が結構ざっくりしてて。でも、そのぶん頭に入りやすい。
なるほどな、と思ったポイント3つ。
・ユダヤ教、イスラム教と違い、キリスト教は当時の国の統治者が律法を自由に作ることが可能だったので、それが西欧諸国の発展につながる。
・プロテスタンティズムの倫理について。
プロテスタントでも特に厳しいカルヴァン派では、救済される人はあらかじめ決まっているのだけど、人は自分が選ばれた者であることを証明するために、より勤勉に働くようになった。
・キリスト教における自然科学との関係。この世界は神が創造したけど、神はここにはもういなくて、人類にこの世は託された。だから、いまは人間が地球の主。だから自由に解明し、加工してもよい。
ここは、自然界のどこにでも神がいると考え、だから自然を怖れ、共存していくものと考える日本人の宗教感とは真逆だな。
なかなかよい入門書でした。
それにしても、新書で30万部というのはすごい!