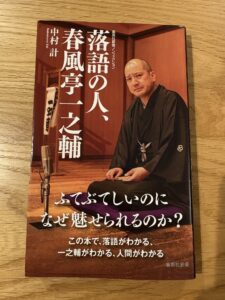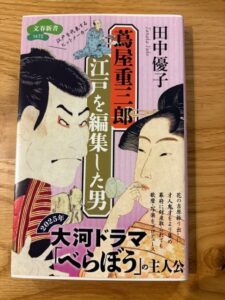新書は面白い⑨
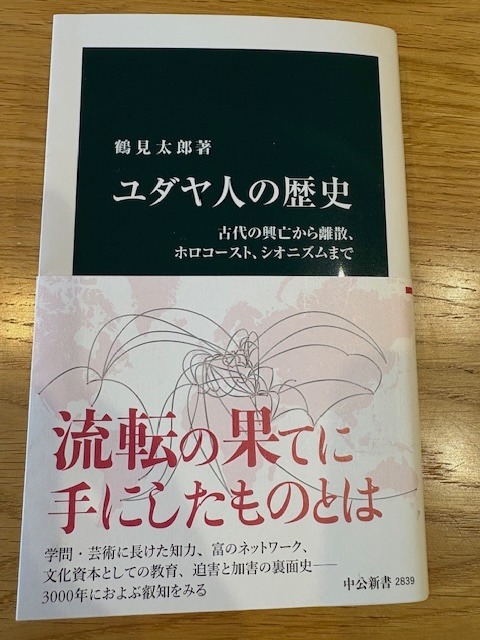
『ユダヤ人の歴史』鶴見太郎 中央公論新書
イスラエルのマクドナルドではチーズバーガーが売られていないのはなぜか?
ユダヤ人に金融業者、商人が多かったのはなぜか。
ユダヤ人とは何か、なぜ影響力があるのか。そしてなぜ迫害されてきたのか。3000年の世界でのユダヤ人の歴史がひと通り理解できる、すごく良い本だった。
すごくざっくり言うと、
ユダヤ人は、ユダヤ人の母から生まれるか、もしくはユダヤ教に改宗したものと定義されている。つまり古代イスラエルからの民族的な側面だけでなく、宗教的側面の両面があるということ。
この宗教的側面、戒律の色が強いのがユダヤ人の特徴。そして象徴的なのがラビの存在。ラビはキリスト教の司祭にあたるが、もっと守備範囲が広くて律法学者でもある。彼らが、ユダヤ教徒がきちんとユダヤの教えを守るよう生活面でも厳しく指導。
例を挙げると、旧約聖書の出エジプト記にある「子ヤギの肉を、その子ヤギを産んだ母ヤギの乳で煮込んで図らない」と書かれていることについて、ラビたちがその解釈を議論した結果、全ての肉と乳製品を一緒に食べることを禁止にした。
だから、チーズバーガーなんでもってのほか。親子丼もNGだね。
あと週末金曜の日没から土曜日没までの安息日(シャバット)。
これは休んで良い日ではなく、「休まなくてはいけない。一切の作業をしてはいけない」日。だから、なんと、電気の操作をする、灯りを消すとか、も禁じられている。
そしてなぜユダヤ人に金融・商業従事者、お金持ちが多かったかと言う理由について
ひとつはローマ帝国ではキリスト教信者は金利をとることを禁じられていたから。金貸しを商売にしてはいけなかったんだね、教会が無利子で貸してたみたい。これは昔英語のテキストで読んだことあるな。
そしてもうひとつの理由が、識字率の高さ。子供の頃から経典を読み込んで教えを守ることが求められていたので、ユダヤ人の識字率が相対的にとても高かったから。へー。
ユダヤ人のことについて語るときに外せない、世界の1700万人のユダヤ人中600万人が犠牲になったホロコーストや、シオニズム運動とパレスチナでのイスラエル国家設立に至るまで。それらはもちろんのこと、ロシア、スペイン、オスマン帝国でのユダヤ人の歴史など、知らなかったことが沢山。世界史の授業でもこういう教え方はしないからね。
売れているみたいです。昨日の朝日新聞によると、トーハン調べの新書部門でなんと1位。
地味なテーマだけど知っておきたかったこと。中央公論新書はそんなテーマを取り上げるのがうまい。